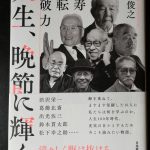日本リーダーパワー史(646) 日本国難史にみる『戦略思考の欠落』(39)日清戦争勝利後の小国の悲哀・日清講和条約後の 「三国干渉の真の首謀者は何と陸軍の恩人『ドイツ』だった。
2016/01/26
日本リーダーパワー史(646)
日本国難史にみる『戦略思考の欠落』(39)
日清戦争勝利後の小国の悲哀・日清講和条約後の
「三国干渉の真の首謀者は何と陸軍の恩人『ドイツ』だった。
前坂俊之(ジャーナリスト)
三国干渉の真の首謀者は何と陸軍の恩人『ドイツ』だった。
日清戦争における日本軍の圧倒的な勝利は欧米列強に衝撃を与えた。ちなみに、日清戦争によるわが国の犠牲者は外地に出征した兵士、軍属は合わせて約17万8000人で、このうち7.5パの約1万3500人が死亡した。戦費は約三億円にのぼり平時の約二十倍である。
この勝利の分け前をめぐる日清講和条約は明治28年4月17日、下関で調印された。
- 朝鮮国の独立(清国の属領を否定)
- 遼東半島(旅順) と台湾の割譲
- 賠償金二億両(邦貨約三億円)の支払
といった内容で、日本側は歓喜にわいたが、大きな落とし穴が待っていた。調印から6日後の23日に突然、ロシア、ドイツ、フランスが連名で「遼東半島を日本が所有することは、朝鮮国の独立を有名無実にし、極東の平和に害を与える」との理由で「三国干渉」に乗り出してきた。
当時、ウラジオストックを基地としていたロシア太平洋艦隊は軍艦12隻、ドイツ軍艦1隻、フランス軍艦1隻の15隻の適合艦隊を組んで、日本周辺海域に派遣して、「三国干渉」拒否の場合は直ちに攻撃するぞと戦闘準備態勢に入った。
日本側は戦争中から米欧列強の介入をある程度は予想していたが、戦争遂行におわれ、介入防止の外交工作は二の次になっていた。その間に、あっというまに戦争はおわり講和会議となったのである。
『戦いは五分の勝利をもって上となし、七分を中となし、十分をもって下となす。五分は励みを生じ、七分は怠りを生じ、十分は驕りを生ず』(武田信玄「甲陽軍鑑」)の通り、「勝ち過ぎは負けに通じる」という勝利のパラドックスにはまった。
イギリスは下関条約で自国の権益が損なわれることはないと判断したことに
加え、ロシアの南下政策を警戒していたことから三国干渉の誘いには乗らなかった。
清国は中国流の外交戦術第一条『遠交近攻』を戦争中から英、米、仏、独、露に猛烈な利権誘導の秘密外交を展開し、三国干渉を実現した。
三国干渉を受けて、日本側に批准延期を要求してきた。批准ができなければ条約は失効する。日本は窮地に立たされた。
伊藤博文首相は23日夜、陸・海軍首脳と緊急会議を開いて対応を協議し、翌24日の御前会議に臨んだ。
明治天皇はいまだ広島の大本営に留まっていた(大本営は27日に京都、29日に東京へ移る)。このため御前会議は大本営で開かれた。
伊藤首相は、今後我が国がとるべき案として3案をあげた。
・第l案 たとえ新たに敵国が増加するも三国の勧告を断固拒絶する。
・第2案 列国会議を開催し、遼東半島問題を協議する。
・第3案 勧告を受け入れ、清国に恩恵的に還付する。
第l案については、陸・海軍とも三国と戦っても勝ち目はないことから、すぐ退けられた。第3案も受け入れられないとの判断に至った。というのも実際に戦い、満州に駐屯している将兵の反発を買うのは必至であり、勝利に沸き返っている国民にも説明がつかない。
伊藤は『英米の日本への友好国の支援を期待して、国際会議の開催を訴える』第2案を強く押し、この第2案を採択した。
下関講和会議で伊藤首相とともに全権を務めた陸奥宗光外相はこの時、病気のため神戸で療養しており、会議には欠席していた。翌日、伊藤は松方正義蔵相を伴って陸奥を見舞った、御前会議の決定を報告、判断を求めた。
結果を聞いた陸奥外相は、「列国会議を開けば、強国の外交戦略に翻弄され、英米への支援期待とは逆の、さらに過酷な要求を突き付けられる可能性が高い。日本に不利となる干渉を招くだけだ」と、第2案に断固反対した。
ロンドンに留学し、弱国の外交史を猛勉強してきた博識の陸奥は次のケースを挙げた。
1877年(明治10年)の露土戦争ではロシアはトルコに軍事的には勝ったが、翌年ベルリンの列国会議で、ロシアのトルコ進出は拒否されてしまった事件があった。このように軍事的には勝利しても外交で失敗して、所期の目的を果さなかったという事例は決して珍しいことではなかった。
しかも、ベルリン会議場合も、三国干渉同様にドイツが首謀であったという事例を陸奥外相は伊藤首相に説明し、第2案に反対したのだ。
この陸奥の建策により、伊藤も考えを改め、第3案の「三国には譲歩するが、清国には一歩たりとも譲らない」2面作戦で対応することにことを確認した。
日本はこの強国連合の恫喝には屈するほかなく、泣く泣く受け入れ4月30日、三国干渉を部分的に受け入れることを三国へ通知。5月4日の閣議を経て、5月10日、遼東半島還付の詔勅が発せられた。そして、国、国民をあげて「臥薪嘗胆」して「三国干渉」の張本人・ロシアへの復讐を誓ったのである。
ところが、三国干渉の真の首謀者はロシアではなくドイツだったのである。
三国干渉にドイツが加わっていたことに陸軍は大ショックを受けた。あのビスマルク、モルトケを神のごとく崇拝し、まねていた日本はドイツのインテリジェンスに「赤子が手をひねられるよう」に裏切られたのだが、その三国干渉の真の首謀者はドイツ皇帝ウイルヘルム2世だったのである。
もともと、ドイツのアジア、中国進出は英仏米ロから比べて大幅な遅れを取っていた。
1872年(明治4年)普仏戦争に勝利すると、武器市場としてアジアへの進出を加速、清国へはドイツ製の「鎮遠」「定遠」など巨大軍艦を海軍士官付きでセットで売り込み指導、日本に対しては陸軍創設のための指導教官メッケルを送りこんできた。メッケルも3年間、陸軍大学校でモルトケ、クラウゼヴイッツの戦略、戦術を教えた後は清国の指導に回わり、同じ手ほどきをしながら、各種情報をインテリジェンス(諜報)していたのである。
こうして、清国や日本を支援してロシアに対抗させる一方、ロシアの東洋進出をも支援して、戦わせて、ヨーロッパでのロシア勢力を駆逐するインテリジェンス(遠謀深慮、謀略)であった。三国干渉の結果、日本から恨まれるマイナスと、将来の清国の領土分割戦争に加わり英国の反対に露仏独の3国連合で対抗して、領土を獲得するメリットをしたたかに計算した上での、三国干渉介入だった。
『黄禍論』を声高に唱えていたドイツ皇帝ヴイルヘルム二世は1895年4月、ロシア・ニコライ二世に宛てた書簡の中で、次のように述べている。
「私はヨーロッパの静寂を保ち、ロシアの背後を守ることに全力を尽くす覚悟である。極東に向けての貴方の行動を、誰にも邪魔させはしない。アジア大陸を教化し、黄色人種(日本人のこと)の侵略からヨーロッパを守ることがロシアに課された将来の大きな務めであることは明らかだからである。
かくして、出来る限り貴方を手助けする覚悟で私が常に貴方のそばにいることを忘れないでほしい。……(さらに繰り返し自分の黄禍に対する憎しみを述べた後)歴史あるヨーロッパのキリスト教文化を蒙古人種(日本人を指す)や仏教の侵略から守ることこそロシアの使命である。」(山口洋一『植民地残酷物語』(カナリアコミュニケーションズ、2015)212P
ビスマルクが岩倉使節団に語った「大国は都合のいい時だけは国際法を遵守を叫び、自国の利益のためには国際法など無視して軍事力を使う」という帝国主義的な恫喝武力外交を駆使したのである。
また、この裏では戦争で負けた清国側は欧米列強に利権をちらつかせて猛然と秘密外交工作を展開して巻き返しをはかって、この最後の逆転劇を仕組んでいた。
戦争には強いが、外交には弱い、インテリジェンスのない日本に対して、ドイツも清国も、1枚も2枚も上手だったのである。
「日本のモルトケ」川上はドイツ、清国に土俵際でうっちゃられた。ただし、大陸にいた全軍を粛々と撤兵させた点では見事な采配を示している。
これの『引き際』を昭和の陸軍と比べてみると、リーダーパワー、決断力がよくわかる。東條内閣は日米交渉での米側最終回答で「中国大陸からの全支那派遣軍の撤退せよ」を突き付けられ、これを拒否して負けるとわかっていた日米戦争に、「清水寺から飛び降りる」賭けで無謀にも突入した。
明治と昭和戦前のトップリーダーの決断と見識の差が「勝利」と「敗北」、「明治史」と「昭和史」の歴史の明暗を分けた。
関連記事
-
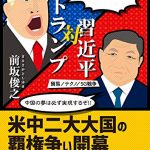
-
『電子書籍 Kindle版』の新刊を出しました。★『トランプ対習近平: 貿易・テクノ・5G戦争 (22世紀アート) Kindle版』( 2019/09/23 )
2019/09/23 米中二大大国の覇権 …
-

-
新刊紹介ー福島の未来に多くの示唆を与える『ふるさとはポイズンの島―ビキニ被曝とロンゲラップの人びと』(旬報社)
新刊紹介 <福島原発事故から2年―福島の未来に多くの示唆を与える> 写真エッセイ …
-

-
『オンライン講座/今、日本に必要なのは有能な外交官、タフネゴシエーターである』★『日本最強の外交官・金子堅太郎のインテリジェンス②] ★『ルーズベルト米大統領をいかに説得したか] ★『大統領をホワイトハウスに尋ねると、「なぜ、もっと早く来なかったのか」と大歓迎された』★『アメリカの国民性はフェアな競争を求めて、弱者に声援を送るアンダードッグ気質(弱者への同情心)があり、それに訴えた』
2011-12-19 『ルーズベルト米大統領をいかに説得したか」記事再録 前坂 …
-

-
『Z世代のための 欧州連合(EU)誕生のルーツ研究』 欧州連合(EU)の生みの親の親は明治の日本女性、クーデンホーフ光子①』★『「EUの父」といわれるのが一九二三年、「汎ヨーロッパ構想」(EUの前身)を提唱したリヒアルト・クーデンホーフ・カレルギーで、クーデンホーフ光子の二男である』
和史電子図書館(著作権フリー) 2015/11/25 『 …
-

-
速報(120)『日本のメルトダウン』『地震多発時代”はまだ始まったばかり!―首都圏の「巨大地震」発生の可能性』―
速報(120)『日本のメルトダウン』 『地震多発時代”はまだ始まった …
-

-
池田龍夫のマスコミ時評(57)●『オスプレイの事故検証抜きで配備を急ぐ』●『原子力委員会が企んだ「秘密会議』
池田龍夫のマスコミ時評(57) ●『オスプレイの事 …
-

-
★10 『F国際ビジネスマンのワールド・ カメラ・ウオッチ(174)』『オーストリア・ウイーンぶらり散歩⑦] (2016/5)『世界遺産/シェーンブルン宮殿』その広大な庭園に驚く(下)。
★10 『F国際ビジネスマンのワールド・ カメラ・ウオッチ(174)』 『オース …
-

-
記事再録/知的巨人たちの百歳学(136)-『酒で蘇生した「酒仙」横山大観(89)の「死而不亡者寿」(死して滅びざるもの寿)
2015/08/30 /「百歳・生き方・死に方-臨終学入 …
-

-
日中韓対立のルーツ『日清戦争』を日本の新聞はどう報道したのかー徳富蘇峰,福沢諭吉、朝比奈知泉らの主張は・①『対朝鮮発言権は日本のみと』(徳富蘇峰)
日中韓対立のルーツ『日清戦争』を日本の新聞は どう報道したのかー徳 …