片野勧の衝撃レポート(50)太平洋戦争とフクシマ(25)『なぜ悲劇は繰り返されるのかー東京大空襲と原発(上)
片野勧の衝撃レポート(50)
太平洋戦争とフクシマ(25)
『なぜ悲劇は繰り返されるのかー東京大空襲と原発(上)
片野勧(ジャーナリスト)
約10万人が犠牲に
約10万人が犠牲になったとされる1945年の東京大空襲から3月10日で70年となる。東京大空襲と原発――。両方を体験された方が福島県石川町にいると聞いて、私は自宅(立川市)から車で出かけた。昨年(2014)6月30日。到着したのは午前11時ごろだった。
「あの日の夜のことを忘れることはありませんでした。しかし、ほとんど語らずにいました」
こう川西恭子さん(86)は静かに語り出した。「あの日」とは1945年3月10日未明のこと。当時、川西さんは世田谷の下北沢に住んでいた。
「ところで……」と言って、川西さんはテーブルの上に1冊の本を置いた。石川町教育委員会編『平和の誓い――語り伝える石川町戦争の記録』である。
8・15終戦から50年の節目に当たる平成8年7月の発刊である。歴史の生きた証言を記録し、次の世代に引き継ぎ、平和の尊さと不戦の誓いを再認識するために編まれた記録集だ。
当時の石川町長は鈴木信夫さんという。彼は「発刊のことば」に、こう書いている。「旧制中学3年の時、学徒動員で横浜の鶴見で発電機の部品を作っていた。その時に東京大空襲に遭い、住んでいた目の前の住宅約20戸が、一瞬にして吹き飛ばされた」と。
戦争は二度と繰り返してはならぬ――。「しかし……」と、こう鈴木町長は続ける。
「50年という長い年月は、あの悲惨な戦争を風化しているようにも思われます。…(中略)この記録集を、一人でも多くの方々に読んでいただき、戦争がもたらす悲惨な結果を、子々孫々に語り継いでいただきたいと思います」
戦争体験の風化。ある種の焦燥感を伴って、戦後、繰り返し叫ばれてきた。しかし、気がついてみると、こうした言葉をほとんど耳にしない。それどころか、国民の基本的人権を無視するような憲法改正、なかんずく戦争放棄などを定めた9条を改正する動きさえあるのだ。
戦後70年。風化が進む戦争の記憶
戦後70年。風化が進む戦争の記憶。空襲、被ばく、太平洋戦争……。それは昔のことに違いないのだが、今も世界中で同じことが繰り返されている。そうであればこそ、これは過去の問題ではない。現在の問題でもあるのだ。
戦争体験者や遺族の高齢化が進む中で、戦争の記憶をどう受け継いでいったらよいのか。子どもたちに、戦争体験をどう伝えていったらよいのか。川西さんも東京大空襲を体験された一人である。
彼女も『平和の誓い――語り伝える石川町戦争の記録』に「恐ろしかった一瞬の悲劇」という題で一文を寄せている。少し、長いが、その要点を記す。
――「けたたましく鳴り響くサイレンと共に、暗闇の中を手さぐりで、われ先にと蒸し暑い防空壕へと急ぐ。ジッとかがんでいると、『ヒューッ、ヒューッ』という焼夷弾の流れ落ちる音。こわさに頭をかかえてちぢまっていた。瞬く間に、赤い火のついた布が庭先に、家に、生垣に、障子に、ひっかかりへばりつき、そして『パァーッ』と燃えあがっていく。
とうとう我が家にも、火がついて燃えあがり、防空壕からはい出るようにして、燃える火をさけ、我が家を振り返りながら逃げた。着の身着のまま。髪の毛が燃えそうになると、綿の入った防空頭巾を用水につけては、頭からかぶり、救急袋を肩からかけて近くの水道局の中に逃げた。
そこにも、焼夷弾が投下されて、塀の中は火の海。父母と上水の土手に逃げていく。またまた、B29の爆弾投下。メラメラ燃える土手をはいあがり、甲州街道をひたすら逃げた。みんなで逃げた土手の下の貯水池の中は、熱さで苦しみもだえて死んでいった浮いた死体で一杯だった」
『平和の誓い』7人の孫にも伝えたい
3・10東京大空襲。一夜にして約10万人が死んだ。川西さんは、この『平和の誓い』という本を東京にいる兄弟や姪っ子に全部、贈った。二度と同じ過ちを繰り返さない願いを込めて。
川西さんは、この『平和の誓い』に書いた内容とほぼ同じ内容の空襲体験を書き残した。平成22年(2010)8月15日。石川町主催の第15回「平和祭の日」に、400字詰め原稿用紙4枚半に自身の戦争体験を自筆で丁寧に書いた。川西さんの証言。
「私には7人の孫がいます。この原稿を、その孫たちに渡しておけば、いつかきっと読んでくれると思って書き残したのです。また、ひ孫にも読んでもらいたいという願いを込めて書いたものです」
こう言って、川西さんは私に、その手書きの原稿を見せてくれた。「もし、土手に逃げていなかったら……。今の私は、そして今の幸せはなかっただろうと思います」
こう話しながら、川西さんは両手で目頭を押さえた。
この原稿は、石川町が平成22年に立てた「平和の像」の下に埋め込まれた。何年か後に、この原稿は開封され、川西さんのもとへ返されることになっているという。
東京大空襲で何もかも失った川西さんは、今、住んでいる石川町の家から約4キロ先の、山に囲まれた平田村に疎開した。終戦のちょっと前だった。
父と母。姉とその3歳になる子どもと一緒に、汽車に乗ってやってきた。車内は混雑していて立ちっぱなし。しかし、途中、茨城県の日立も空襲に遭い、列車はストップ。夜が明けるまで列車の中に閉じ込められた。
――その時、おいくつでしたか。
「18歳か19歳になるところでしたかね。当時、女学校に行っていましたが、学徒動員で勉強はほとんどやりませんでした。青春はなかったですね」
食糧難の中を生きた
防空壕の中で震えながら、爆弾の音を聞き、食糧難に苦しんだ川西さんの、少女のころの記憶は衰えていない。
「こんなことを言ったら申し訳ないのですが、戦争に行かれて亡くなられた方々だけが犠牲者ではないのです。私たちも犠牲者です。残された家族はごろ寝で、食べ物はこうりゃんのおにぎり1個。本当に食べるものはありませんでした」
戦後の食糧難の中、川西さんはひたすらはいあがろうとしてきた。昭和23年(1948)、石川町の小学校の校長から「先生が足りないから来てくれないか」と言われた。
「教員なんてできないと、父に言ったのですが、何でもやらなければ食っていけないのだから、頑張りなさい、って言われて引き受けました」
結局、川西さんは36年間、教員生活を送った。結婚は昭和25年(1950)。
川西さんは戦争体験のほかに、もう1遍、寄稿している。東日本大震災の記録集『伝えたい 福島の3・11』。福島県退職女性教職員あけぼの会のメンバーが編んだ記録集である。
川西さんは日記を綴っていた。その日記を抜粋しながら、見たまま、感じたままを書いている。たとえば、震災から2カ月余の平成23年(2011)5月の、とある日の日記。
「東北大震災の津波で亡くなられた方、いまだに行方不明の方、家・車まで持ち去られてしまった方、そして津波で逃げる様子の映像を見た。思えば私も、60余年前、若い娘時代のころに、東京大空襲に遭い、日本橋の道路一杯にたおれている亡骸(なきがら)に、手を合わせながらまたいで逃げた時の様(さま)を思い出し、それとダブって走馬燈のように頭の中が一杯になり、複雑な気持ちでティッシュの箱をつかみ、涙を払いつつテレビの前から、動けなかった」
3・10東京大空襲と3・11東日本大震災
3・11東日本大震災。息が詰まるほどの惨状は、10万人が一夜にして死んだ東京大空襲の焼け野原に似ていると、川西さんは言う。確かに似ている。それは、どちらも一瞬にして町が破壊されたという点だろう。
わずか2時間余りで東京の下町を灰燼と化した3・10東京大空襲。一方、目に見えない放射能で、強制的に立ち退かせ、ゴーストタウンと化した福島原発事故。私は、この4年間、7、8回、フクシマに足を踏み入れたが、無人と化した町並みは、まさに戦場を思わせる絶望的な情景だった。
私はフクシマを歩き、聞き書きを重ねている。いつも聞く質問が一つある。戦争の時と今回の大震災の時とでは、その苦しみ、悲しみはどう違いますか? 戦争と原発に共通する問題点は何ですか? 川西さんは答えた。
「私たち石川郡の教職員は福島第1原発の建設に大反対しました。バスをチャーターして何度か原発の立地場所まで行きました。しかし、すでに遅かったです。政府が全部、お膳立てしていて、手遅れでした。戦争も原発も国策で、それに対して庶民は無力でした」
3回目に行った時は敷地に土台も出来上がっていた。
「地元にすれば、原発のおかげで随分、いい思いもしたのでしょうが、今はみんな複雑な思いだと思います。建設を断念させられなかった私たちも複雑です」
2度も国策によって人生を翻弄された
戦争と原発――。二度も国策によって、人生を翻弄された福島の人々。放射能汚染で、いつ戻れるのかも分からない。住み慣れた土地を奪われることなど誰が想像しただろうか。
ふるさとを失い、家族と離散し続ける人々に、東京大空襲を生き延びた川西さんの思いは重なる。その語る一言一言の言葉の持つ意味は重い。
「戦争も原発も、絶対に次の世代に残すべきではありません」
近くの山にはたくさんの山菜がある。娘婿の川西正昭さん(68)は山が好きで、よくフキノトウや山菜を採ってくるという。それを天ぷらにして孫、ひ孫と一緒に食べることが楽しみという。川西さんは言った。
「これが一番の平和なんです」
3・11から4年。どうする会津!
もう一人、東京大空襲に遭った人がいるというので、出かけて行った。年の瀬も迫った昨年(2014)12月28日。会津若松は雪が降っているというので、この日はJRの高速バス(深夜便)を利用した。新宿発は午後11:00、会津若松着は翌29日午前5:00――。
取材予定時間は午前9時。時間がたっぷりあったので、会津若松駅近くの、とあるホテルで休憩を取った。ロビーに置いてあった地元の情報誌『会津(あいづ)嶺(ね)』。私は3人の女性による2015年新春座談会「女性から見た会津」に引きつけられた。
大河ドラマ『八重の桜』も終わり、さて、会津にとって今年はどんな年になるのだろうか。3・11以降、どうしたら会津が元気になれるのか、50年後の子どもたちのために何ができるのか。
3・11から4年。どうする会津! 会津に対する熱い思いは、三人三様、さまざま。ある人は観光だけではなくて、「人づくり」の視点が大切と言う。また、ある人は生活者のプロである主婦、女性の感性を生かそう。さらに、ある人は歴史だけが会津の魅力じゃない、古くて新しい会津の魅力はいっぱいあると語る。
会津藩は損得では動かない――司馬遼太郎
この情報誌『会津嶺』に、ある歴史家が「磐梯山から俯瞰した会津藩」というエッセーを書いていた。その中で司馬遼太郎の会津藩のことにも触れていた。
「会津藩というのは、封建時代の日本人がつくりあげた藩というもののなかで最高の傑作のように思える」(『歴史を紀行する』)
つまり、藩をひとつの芸術品とみれば、その完成度は他藩の追随を許さないであろうと。その理由は、一糸乱れず行動する美学が規範であって、会津藩は損得では動かないというのだ。
私はホテルの最上階から見た会津の風景に圧倒された。会津の悲劇はどうして生まれたのか。その悲劇を決して忘れてはならない――。そんなことを考えていたら、もう時計の針は朝の8時半を回っていた。
福島第1原発から約1.5キロ
午前9時。ホテルのすぐ後ろにあるマンションで、その人は待っていた。吉田信雄さん(78)と、その妻・恵(え)久子(くこ)さん(72)。
――3・11。その時、どこにおられましたか。信雄さんは答えた。
「自宅にいました。女房と父母の4人。それに孫が3人の7人でした。本棚が倒れて、父は本の中に埋もれていました。壁も落ちました」
吉田さんの家は福島第1原発から約1.5キロ。避難はどうされたんですか。
「避難せよ、と町では呼びかけていたようですが、我が家は道路からちょっと奥へ入った、こんもりしたところにあったものですから、聞こえませんでした」
――原発事故については?
「地震の時、揺れが激しくて原発のことは全然、頭にありませんでした。ましてや、メルトダウンを起こすなんて、想像もしていませんでした。家には1晩いましたが、隣近所は誰もいない。町のスポーツセンターへ行きましたら、人がいなくて、車がいっぱい。みんな避難したあとだったのです。そこで初めて原発がおかしいということを知りました」
信雄さんは父と孫3人を大熊町の車に、また恵久子さんはおばあちゃんを自衛隊のトラックに乗せてもらって田村市へ向かう。恵久子さんは言う。
「途中、おばあちゃんは気分が悪くなって、降ろしてくれと。もう死んでもいいと言い始めました」
そこへ大熊町の人がきて、車を乗り換えて今度は三春町の体育館へ。一方、信雄さんらは田村市の総合体育館へ。信雄さんと恵久子さんの行き先が別々になった。携帯がつながらず、一時、連絡が途絶えたが、13日、三春町の体育館で出会った。
ここで3日間いて、その後、体育館の生活がきびしいので高齢の両親だけ千葉にいる弟のところに約2週間、滞在させた。その間、孫たちはお母さんと一緒に郡山へ。その後、信雄さんらは4月3日から約3カ月間、会津大江戸温泉に避難。吉田さん一家は各地を転々として、ようやく7月1日に現在のマンションに落ち着いたという。
つづく
関連記事
-

-
『リーダーシップの日本近現代史』(255)記事再録/ 『歴史有名人の長寿と食事①天海、御木本幸吉、鈴木大拙、西園寺公望、富岡鉄斎、大隈重信』
2011/07/19百歳学入門(30)/記 …
-
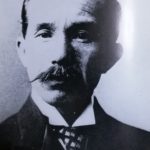
-
『オンライン講座/ウクライナ戦争と日露戦争を比較する➂』★『『日本最強の外交官・金子堅太郎のインテリジェンス①>★『日露戦争開戦の『御前会議」の夜、伊藤博文は 腹心の金子堅太郎(農商相)を呼び、すぐ渡米し、 ルーズベルト大統領を味方につける工作を命じた。』★『ルーズベルト米大統領をいかに説得したかー 金子堅太郎の世界最強のインテジェンス(intelligence )』』
2021/09/01 『オンライン講座/日本興 …
-
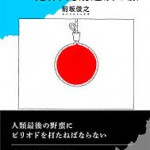
-
『オンライン/<裁判員研修ノート④>『明日はわが身か、冤罪事件』ー取調べの可視化(取調べの全過程録画)はなぜ必要か、その理由
2010/01/18 記事再録 前坂 俊之(毎日新聞記者) …
-

-
『リーダーシップの日本近現代史』(305)★『3・11国難リテラシー⑩「糸川英夫いわく」★『➀なぜ事故は起きたのか(WHY)ではなく「事故収束」「復興・再生」の「HOW TO」ばかりの大合唱で、これが第2,3の敗戦につながる』②『すべての生物は逆境の時だけに成長する』③『過去と未来をつなげるのが哲学であり、新しい科学(応用や改良ではなく基礎科学)だとすれば、 それをもたない民族には未来がない』
2011/05/18 & …
-

-
日本メルトダウン(1000)ー『1人あたり」は最低な日本経済の悲しい現実/日本の生産性は、先進国でいちばん低い』●『日本人は「人口急減の恐怖」を知らなすぎる 今後はフリーフォールのように急減していく』●『原発廃炉費用の転嫁で電気料金はどれだけ増えるのか 賠償費用も転嫁されると家庭の負担はさらに増加』●『 カジノを合法化してパチンコに課税せよ『 日本は世界最大の「脱法ギャンブル大国」(池田信夫)』★『「日本を殺せ」が米国で大ヒット、東京だった次の原爆 オライリーが描く「逆説の日米戦争」』
日本メルトダウン(1000) 「1人あたり」は最低な日本経済の悲しい現実 …
-

-
日本メルトダウン脱出法(601)【高齢化する欧州には移民の新しい血が必要だ(英F・T紙)『コラム:経済成長なき「豊かな生活」は可能か
日本メルトダウン脱出法(601) ◎【高 …
-

-
日本メルトダウン脱出法(579)●『エボラより怖い「EV-D68」、全米で子供に感染」●「Google Glassで脳波の動きだけで写真撮影」
日本メルトダウン脱出法(579) &nbs …
-

-
日本リーダーパワー史(629)日本国難史にみる『戦略思考の欠落』(22) 『川上操六は日清戦争は避けがたいと予測、荒尾精の日清貿易研究所を設立しで情報部員を多数養成して開戦に備えた』。
日本リーダーパワー史(629) 日本国難史にみる『戦略思考の欠落』(22) …
-

-
日本リーダーパワー必読史(742)『歴史復習応用編』ー近代日本興亡史は『外交連続失敗の歴史』でもある。明治維新の国難で幕府側の外務大臣(実質首相兼任)役の勝海舟の外交突破力こそ見習え➊『各国の貧富強弱により判断せず、公平無私の眼でみよ』●『三国干渉くらい朝飯前だよ』』●『政治には学問や知識は二の次、八方美人主義はだめだよ』●『国難突破力NO1―勝海舟(75)の健康・長寿・ 修行・鍛錬10ヵ条」』
2016年10月28日/ 日本リーダーパワー必読史(742) 明治維新 …
-

-
高杉晋吾レポート⑱ルポ ダム難民②超集中豪雨の時代のダム災害②森林保水、河川整備、住民力こそが洪水防止力
高杉晋吾レポート⑱ ルポ ダム難民② 超集中豪雨の時代のダム災害② …
