片野 勧の震災レポート① 『戦災と震災ーなぜ、日本人は同じ過ちを繰り返すのか』
片野 勧の震災レポート①「3/10から3/11へ」
戦災と震災・なぜ、日本人は同じ過ちを繰り返すのか
片野 勧(フリージャーナリスト)
大津波にのみ込まれて壊滅した街の光景と、戦災で焼け野原と化した街の姿――。
戦前、戦中を生きた多くの人たちは、この二つの光景を重ね合わせて、戦後とは何だったのかと改めて思いを巡らせたに違いない。また福島第1原発事故による放射能被害を見て、広島と長崎への原爆投下を想起した人も多いだろう。
私は、そうした人々の思いと、戦後の復興がどのようにしてなされていったのかを求めて、東北の被災地を歩いた。むろん、メディアから依頼された取材ではない。現場はどうなっているのか。この目と耳で確かめたいと、とりあえずビデオカメラとカセットテープとノートを持って出かけたのである。
宮城県名取市。思わず、息を呑んだ。海岸の街は一面、瓦礫の置き場の山と化していた。その光景はテレビで何度も見ていたが、テレビで見た光景と自分の目で確かめた光景とは、また別の世界だった。
不思議な沈黙、奇妙な臭い……。道路はあるが、街がない。瓦礫の置き場から火が出たというニュースが流れた。ヘドロや重油まみれの木材が交じる津波被災地の火災は、まるで大空襲で燃え盛った東京の街の様相と似ていた。
津波で呑みこまれた街の木造家屋は土台しか残っていない。岩がむき出しになっているだけだ。ところどころにコンクリートの建物が骸骨のように立っていた。この状況に接して、私は自然の猛威に文明がすべて否定されたように感じた。
◎私は「空襲・戦災を記録する会」全国連絡会議で各地の戦場写真を数多く見てきた
が、どんな戦場でもこんなすさまじい光景を見たことがない。瓦礫の中に墓石が横倒しになっていた。その中に仏像が一体、微笑を浮かべて立っていた。
津波は凶暴な力で一瞬にして平穏な日常を変えた。地肌がむき出しになり、荒廃した光景は、まさに震災という名の「戦場」ではないのか。
石巻市。製紙工場も大きなダメージを受けた。紙製品を運んでいたコンテナ貨車、出荷されるはずだった紙製品のロールが津波の力であちらこちらに散乱していた。特に紙を運んでいた鉄道の被害は甚大。線路はぐにゃぐにゃに折れ曲がり、赤い車両はレールから外れ、大きく倒れていた。67年前の東京大空襲でも鉄道が狙われ、都民の足が奪われたが、今回の津波の比ではない。
福島県南相馬市小高区は東京電力福島第一原発から半径20キロ圏内で立ち入り禁止区域。今なお人がいない無人の街だ。自然の恵みを奪われ、安らぎの日常も自由も失った。
村人は牛の乳を搾り、山菜を採り、酒を飲み、語り合って来た。
結婚式や葬式も行ってきた。それが、ある日、突然、「原発が危険になったから避難せよ」と、まるで豚を車に乗せるようにバスに押し込められ、行き先も分からないまま集団移住させられてしまう。さらにそこも危険になったから二次・三次の移住を強いられる。
もちろん、集団移住先へは犬や猫は連れて行かれない。牛や馬、豚、鶏も然り。田園地帯の穏やかな日常が一方的に断ち切られ、夢も希望も踏みにじられたのである。こうした福島の集団移住を見ていると、戦前、戦中、中国大陸から引き揚げる子どもたちや国内の親戚を頼って疎開する子どもたちと、あまりにもよく似ていることに気づく。
戦争が激しくなって丈夫な男の人はほとんど出征してしまい、防火訓練、消火訓練は女の人の手に。そのうち住んでいるところが建物疎開の指定になり、その指定に当たった家の子供たちは両親の故郷や知人を頼って疎開するようになった。縁故のない人は新たに東京の地で住宅を探して引っ越していった。
福島第一原発の事故で福島県から県外に避難した人は6万人を超え、うち3割は東京周辺の1都3県。東京都江東区の国家公務員宿舎・東雲住宅では、全国で最も多い約1200人が慣れない生活を送っている。
福島原発から25キロの南相馬市原町区。1971年に発電を開始してから今日まで福島原発の技術的危うさと、その管理運営の問題点を告発し、警鐘を鳴らしてきた詩人がいる。若松丈太郎氏だ。彼は『福島原発難民』(コールサック社)や『ひとのあかし』(清流出版)などを出し、南相馬市から原発の危機を発信し続けている。
「ひとは作物を栽培することを覚えた/ひとは生きものを飼育することを覚えた/作物の栽培も/生きものの飼育も/ひとがひとであることのあかしだ/あるとき以後/耕作地があるのに作物を栽培できない/家畜がいるのに飼育できない/魚がいるのに漁ができない/ということになったら/ひとはひとであるとは言えないのではないか」(『ひとのあかし』)
また事故を隠し続けてきた国や東電の体質から、いずれ福島原発もチェルノブイリのようになり、南相馬市周辺も放射能で汚染されると警告してきた。彼は言う。
「日本が今、直面している問題は67年前の戦争時とそっくりですよ。勝てない戦争なのに、『勝った、勝った』と煽って、事実を隠していたのですから」
3・11「東日本大震災」以降、日本のメディアは朝から晩まで被災地の報道で満ちていた。とりわけ、東電や政府から流される“大本営発表”を鵜呑みにし、無定見な情報を流したことは、太平洋戦争時の国民に対する情報操作と同質。
1943年1月のガダルカナル島からの撤退、1944年6月のマリアナ攻防戦でもはや戦局の帰趨は絶望的になり、多数の戦死者や餓死者が出て、誰が見ても敗戦は明らかだったのに、「がんばろう!日本」などの標語が飛び交い、感動的な話題を満載していた。しかし、実態は全く逆だった。政府は情報を隠蔽していたのである。
●「節電しよう」「15%削減しよう」は「ゼイタクは敵、ガマンは美徳」の
プロパガンダと同じ。
プロパガンダと同じ。
同様のことが福島原発でも起こっていた。地震直後の3月12日早朝、福島県浪江町は政府の指示を受け、役場機能を町北西部の津島地区に移転し、町民を津島地区や福島第一原発から半径10~20キロ圏に避難させた。しかし、身を寄せた同町津島地区が実は放射性物質が降り注ぎ、放射線量が高かったことが後になって分かったのである。
RPEEDI(スピーディー)。放射性物質の流れ方を予測するデータだが、このSPEEDIが総理官邸に届かずにいたらしい。
しかし、震災から4日目の3月14日午前10時40分、放射性物質の拡散を予測する機関「原子力安全技術センター」からSPEEDIが米軍に届いていたというのだ。結果的に放射性物質が飛散した方向と重なり、住民は外部被ばくしたのである。再び、若松氏の言。
「危険なら、当然避難指示があると思っていたのに、これでは住民は見捨てられたも同然ですよ」
若松氏の憤りを聞いていると、戦前・戦中と問題の構造は驚くほど似通っていることに気づく。国家が国民を欺いているのに、権力は巧みに争点をすり替え、マスコミも追従したこと等々。
また「節電しよう」「15%削減しよう」と2011年の夏、福島第一原発事故による電力不足から東京電力はもとより、政府も政治家もマスコミも一丸となって呼びかけた。その呼びかけを聞いていると、戦時中の「ゼイタクは敵、ガマンは美徳」というプロパガンダを思い起こす。
節電の大合唱は戦意高揚と物資の調達のために家庭の鍋釜まで供出させた戦時体制下とそっくり。猛暑の中、自宅のエアコンをつけず熱中症になった老人もいた。私自身も計画停電のため、2度、暗闇の生活を経験した。それに疑問を挟もうとすると、異端児扱いされそうになる。
津波が町や村を根こそぎ押し流した3・11「東日本大震災」。なお決死の冷却作業が続く福島第一原発の事故はチェルノブイリ以上の例として歴史に刻まれるだろう。日本の敗戦も我々に決定的な歴史を刻んだ。
戦争末期、日本の都市という都市は米軍のB29爆撃機によって木っ端みじんに焼かれた。そうした中、東北地方の空襲は1945年8月15日の無条件降伏前の7月と8月に集中した。一般人を狙い、戦意喪失を目的とした無差別殺戮攻撃である。
宮城・仙台空襲は7月10日未明。岩手・釜石の艦砲射撃は7月14日と8月9日の2回。青森空襲は7月28日。ただし、福島・郡山空襲は4月12日正午前後、保土谷化学工場その他の工場に対する精密爆撃だった。そのころ、米軍は主に軍事工場を狙っていたためである。
日本のように権力機構(政治家、官僚、マスコミ)が強大で庶民が無権力の国では、大空襲や原爆投下の時もそうだったが、老人や子供、女性など弱い立場の人々に被害がしわ寄せされる。東日本大震災の死者の64・4%は60歳以上の人々である。
敗戦濃厚な日本に対して続けられた米軍の容赦ない空襲。しかし、何よりも日本の指導者が終戦の決断を遅らせたことが戦禍を広げ、犠牲者を増やしたことはいうまでもない。
第2次大戦が残した教訓は“決断”である。今、震災復興をずるずると先延ばしして、決断できないのは戦前の政府とそっくり。そのことによって、国民を欺く大本営発表という悲劇が生まれたことを忘れてはならない。
原爆死没者慰霊碑には「安らかに眠って下さい 過ちは 繰返しませぬから」と刻まれている。
先の大戦に突き進んだのも、バブル経済に踊ったのも、そして今回の原発事故も官僚や専門家集団、政治家に委ね、それを傍観し狂奔してきた我々日本人の倫理と規範の敗北である。我々は被害者であると同時に加害者でもある。そのことを厳しく見つめ直さない限り、またどこかで同じ過ちを繰り返すだろう。
(フリージャーナリスト)
●『今一番求められるのは<社会の木鐸>である―
反骨のフリージャーナリスト・松浦総三論(片野勧)』
反骨のフリージャーナリスト・松浦総三論(片野勧)』
●新刊『明治お雇い外国人とその弟子たち―日本の近代化を支えた
25人のプロフェッショナル』(片野勧著)
25人のプロフェッショナル』(片野勧著)
関連記事
-
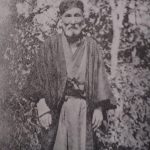
-
「Z世代のための『人生/晩節』に輝いた偉人伝』★『日本一『見事な引き際の『住友財閥中興の祖・伊庭貞剛の晩晴学①『「事業の進歩発達を最も害するものは、青年の過失ではなく、老人の跋扈(ばっこ)である。老人は少壮者の邪魔をしないことが一番必要である』★『老人に対する自戒のすすめ』
2010/10/25 日本リーダーパワー史( …
-

-
速報(394)『日本のメルトダウン』『北朝鮮の核実験がもたらすもの―田中 宇』●『もはやイノベーションは大企業からは生まれない?」
速報(394)『日本のメルトダウン』 ●『北朝鮮の核実験がもたらす …
-

-
『オンライン100歳学講座』★『 全財産をはたいて井戸塀となり日本一の大百科事典『群書索引』『広文庫』を出版した明治の大学者(東大教授)物集高見(80歳) と物集高量(朝日新聞記者、106歳)父子の「学者貧乏・ハチャメチャ・破天荒な奇跡の物語」★『生活保護、極貧生活でも飄々とした超俗的な生き方に多くの人々は百歳老人の理想像を見て、その知恵と勇気に感動した』
前坂 俊之(ジャーナリスト) 物集高見が出版した大百科事典『群書索 …
-

-
日本リーダーパワー史(622) 日本国難史にみる『戦略思考の欠落』 ⑯ 『川上操六参謀本部次長がドイツ・モルトケ参謀総長に弟子入り、 ドイツを統一し、フランスに勝利したモルトケ戦略を学ぶ②
日本リーダーパワー史(622) 日本国難史にみる『戦略思考の欠落』 ⑯ 『川 …
-

-
日本メディア(出版、新聞、映画など)への検閲実態史②『満州事変と検閲の実態を調べる。前坂俊之著「太平洋戦争と新聞」(講談社学術文庫、2007年)より。
満州事変と検閲の実態を調べる。以下は前坂俊之著「太平洋戦争と新聞」 …
-

-
日露300年戦争(5)『露寇(ろこう)事件とは何か』★『第2次訪日使節・レザノフは「日本は武力をもっての開国する以外に手段はない」と皇帝に上奏、部下に攻撃を命じた』
結局、幕府側の交渉役の土井利厚生https://ja.wikipedia.o …
-

-
『リーダーシップの世界日本近現代史』(294)★『 地球温暖化で、トランプ対グレタの世紀の一戦』★『たった1人で敢然と戦う17歳のグレタさんの勇敢な姿に地球環境防衛軍を率いて戦うジャンヌダルクの姿がダブって見えた』★『21世紀のデジタルITネイティブ」との世紀の一戦』★『2020年がその地球温暖化の分岐点になる』
地球温暖化で、トランプ対クレタの戦い』 …
-

-
日本リーダー/ソフトパワー史(658)『昭和の大宰相・吉田茂のジョーク集』①「歴代宰相の中で一番、ジョーク,毒舌,ウイットに 富んでいたのは吉田茂であった。
日本リーダーパワー史(658) 『昭和の大宰相・吉田茂のジョーク集』① 歴代宰相 …
-

-
<F国際ビジネスマンのワールド・ニュース・ウオッチ(212)>『エアバッグのタカタが1兆円の倒産』★『Takata Saw and Hid Risk in Airbags in 2004, Former Workers Say – NYTimes.com』★『本件は、日米のジャーナリズムが誰の味方をしているか?が明確に現れた深刻な事件です。 本当に情けないの一言です。』
<F国際ビジネスマンのワールド・ニュース・ウオッチ(212)> Takata …
-

-
裁判員研修ノート⑧ 冤罪、誤判と死刑を考える②-裁判官と法務大臣の胸の内
裁判員研修ノート⑦ 冤罪、誤判と死刑を考える②-裁判官と法務大臣の胸の内 …
