片野勧の衝撃レポート『太平洋戦争<戦災><3・11>震災⑲ なぜ、日本人は同じ過ちを繰り返すか』 原町空襲と原発<下>
2015/01/01
太平洋戦争<戦災>と<3・11>震災⑲
『なぜ、日本人は同じ過ちを繰り返すか』
原町空襲と原発<下>
片野勧(ジャーナリスト)
■常磐線の全面復旧のメド立たず
「原町空襲を思い出しますよ。あれは戦争だったが、今回は津波という天災だったけれども……」
南相馬市原町区北町にある自宅で、菅野清二さん(76)は電話で語り始めた。菅野さんは元小学校教諭で、現在、「原町絵本と童話の会」代表。
「原発と空襲の関係でいえば、原ノ町駅は原発で不通になり、空襲で破壊されました」
福島県内の常磐線は相馬(相馬市)―原ノ町駅間(20・1キロ)が2011年12月に運行を再開したが、相馬―浜吉田駅(宮城県亘理町)間(22・6キロ)は津波被害などで不通のまま。
特に上り線は福島第1原発から近く、放射線量の高い地域を通るので全面復旧の見通しは立っていない。その上、一般の自動車も通れないのが現状である。
1945年8月9日の2回目の原町空襲。猛烈な機銃掃射の中、菅野さんは家族と一緒に家の裏の竹藪のそばに作っておいた防空壕の中へ飛び込んだ。防空頭巾を被って、身を固くしていた。当時、原町国民学校3年生。(以下、「はらまち九条の会」ニュースNo.38を参照させていただく)
そのうち、ドドーンと壕が揺らいだと同時に菅野さんは壕の床にベシャーンと圧し潰された。
「一瞬、何も分からなくなりました。ふと、気がつくと心臓も体も動いていました。『ああ、俺は生きている』という実感を持ちましたね」
壕の暗闇の中に母の顔が見えた。
「その時の安堵感と嬉しさは、今も忘れません」
敵機が飛び去ったあと、外へ出て驚いた。壕のすぐそばに爆弾で掘られた大きな穴が空いていた。柿の木や杉の木、竹などは切り取られていた。爆弾の破片もあちこちに落ちていた。
「もし、爆弾がもう数メートル近くに落ちていたら、一家は皆、死んでいたかもしれません」
生死は紙一重――。そう思うと、生きているのが奇跡に思えた。
その日の午後5時頃、原町紡績工場が真っ黒な煙と、真っ赤な炎をあげて燃え上がった。ただ呆然と眺めるほかなかった。燃え尽きるまで火は鎮まず、3日3晩燃え続けたという。
その光景と、今回の津波・原発事故で抗いようのない力に立ちすくむ人々の悲しみが重なる。
菅野さんは燃え続ける原町紡績工場を背に、石神村信田沢に避難した。その夜は杉林の中で、畳を屋根形に合わせ、蚊に食われながら寝た。この8月9日の空襲で3人が亡くなった。
■空襲で破壊された原ノ町駅と重なる
翌8月10日。3回目の原町空襲である。この日、時計の針は朝の10時を少し回っていた。原ノ町駅にグラマン1機が500メートル上空から列車に突っ込んできた。ひとたまりもなく、機関車はやられて運行不能となった。
この空襲で6人の鉄道員が殉職された。いずれも、原ノ町機関区構内の防空壕の中だった。そのほか駅構内では、もうひとりの老女が亡くなった。空襲によって破壊された原ノ町駅の情景と、津波・原発事故で常磐線沿線が不通になったことも、また重なる。
営々と築き上げてきたものが一度に失われた。何よりも、日本の社会自体を変えたのが、福島第1原発で発生した事故だ。
「この原発を建てるとき、私は宮城県から来たばかりで、よくわからなかったが、教職員組合や町の有志が反対していました。しかし、政府は絶対大丈夫だといい、東電も『絶対安全なものをつくる』といって建てたのです。人間のやることだから、『絶対安全』ということはありません。原発は一歩間違えれば、大変な被害が出るのに……」
「絶対安全」のはずの原発が炉心溶融を起こし、水素爆発が続いた。10キロ、20キロと警戒半径は広がり、住民は避難し、家族や地域の絆はバラバラに分断されてしまった。日本はなぜ、原発を持ったのか。高度成長のためにはエネルギーが必要だったと、多くの識者は語る。
しかし、繁栄に向けて走り続けた果てにたどり着いた社会の姿は、言いようのない虚脱感と閉塞感に満ちている。その代償はあまりにも大きい。それなのに、日本はまた原発を商品として海外に売り込もうとしている。菅野さんに聞いた。
――安倍首相は「日本の原発は世界一安全だ」と言って、トルコのエルドアン首相との間で原発輸出に向けた原子力協定を結びましたが……。
「でも、外国に原発を売る前に、やることがあるだろう。爆発させた自国の原発をきちんと処理することが先ですよ」
と菅野さんは怒る。その怒りの声は、原発事故で古里を失った立場から原発をセールストークの手段に使われては、かなわないという強いメッセージにも聞こえる。
事故の原因調査が不十分な段階で、安倍首相は何を根拠に「日本製の原発は世界一安全だ」と断定できるのか。もし、輸出先で事故が起きたら、誰が損害賠償の責任を負うのか。日本政府、つまり我々の税金で払えというのか。
■子ども達を平和の語り部に
ところで、菅野さんは長く小学校(大甕小学校や原町第一小学校)の教員をしてきた。その間、学区内の空襲・戦災体験を子供たちの手で発掘しながら、平和教育を行ってきたユニークな先生だ。
昭和50年(1975)、復帰後まもない沖縄で教育研究会全国集会が開かれた。そこでは広島・長崎の原爆、沖縄戦、各地の空襲等の戦禍の悲惨さが語られ、平和の尊さが訴えられた。
その中で菅野さんも「子ども達を平和の語り部に」という報告をした。その報告リポートを抜粋すると――。(以下、前掲書『原町空襲の記録』から)
「戦争の悲惨さを教えようという時は、広島や長崎、あるいは東京大空襲や沖縄戦などの写真を数枚見せただけで、子供達は目をおおってしまいます。しかし、だからといってそれだけで戦争の悲惨さがわかったということにはならないと思うのです。…(中略)沖縄や広島から遠く離れた東北のいなか町にも戦争があったのだと、実感させるための取り組み、つまり掘り起こしの仕事が沖縄や広島を正しくわからせる意味からも必要なのだと思うのです」
さらに、こう綴っている。
「平和を永遠なものにするために、私達は、戦争の悲惨さを語りつたえて行かなければなりません。戦争体験の風化が言われ、又、体験者が年々少なくなる現在は、今まで以上に戦争体験の継承を考えなくてはいけないと思います。その継承者になるための基本は、やはり、父母や祖父母などから話をきくということはあると思います。…(中略)文章にまとめられる場合は稚拙なものになっても掘り起こすという過程が大事だと思うのです」
■子供たちの戦争体験の聞き書き
このリポートには、いくつもの掘り起こしの例が収められている。たとえば、鹿山ひとみさん(大甕小学校5年生)の聞き書き。
「今日、おじさんに戦争の話を聞かせてもらった。戦争についてはいくらか自分で調べていたので、私の知っている話かなと思って聞いたら、ぜんぜんちがう話だった。おじさんは戦争の時、船でガダルカナル島に行ったり、インパールという所で戦ったり、あっちこっちで大変な戦争をしていた。その中で私が一番びっくりして聞いた話は人間が腸を出して死んでいたり、死体がばらばらにふっとんだり、ずがいこつがふっとび皮だけが残っていたという話だった。私はおじさんの話を聞いて、戦争は人間を殺すだけでなく、人間の心も殺してしまうおそろしいものだと思った」
これは菅野さんの準備した素材「各地を転戦した用務員のおじさんの話」に反応して書かれた感想である。掘り起こされた子供たちの体験は、それだけでも十分価値ある記録だが、菅野さんの指導はさらに深化されていく。
「それが個々ばらばらであっては、経験は個人的なものになってしまいます。さらに共通化するために整理したり、まとめたりすることが大切です」
菅野さんは友達の文について、家の人に話を聞いたり、認識を深めたりしたという。そして出来上がったのが、1冊の文集である。その中でユニークなのが「学区の戦災地図づくり」。菅野さんはこう述べている。
「子供たちの聞き取りをもとに学区の戦災地図を作りました。まだ不十分ですが、少しずつくわしいものにしたいと思います」
「まだ不十分だが、少しずつくわしいものにしたい」――菅野さんの、この言葉の持つ意味は重い。歴史を掘り起こすとは何か。戦争体験を次世代に継承していくこととは? 私は菅野さんの話を聞いて、これは、いかに難しいものであるかを改めて知った。
■栃木の宇都宮空襲でも
私事で恐縮だが、かつて私も栃木県で「宇都宮市戦災を調査する会」を立ち上げ、事務局長として『宇都宮空襲・戦災誌』と『あの日の赤い雨』の2冊を編集したことがある。とくに後者の『あの日の赤い雨』はサブタイトルにあるように、「父母から聞いた子どもたちの空襲体験記録」である。
空襲を直接体験した父母たちが綴ったもの――つまり「事実」をありのままに捉えたものが、『宇都宮空襲・戦災誌』であるとすれば、戦争を知らない子どもたちが、父や母から戦争体験を聞き、それを生活の場で具体的に位置づけ編集したものは、「創作」とみなすことができるかもしれない。それが戦争体験の継承につながるのか、一抹の不安はあった。
しかし、子どもたちが懸命になって、“あの日”の夜(1945年7月12日の宇都宮空襲)のことを父母(なかには近所のおじいちゃん、おばあちゃんから聞いたものもあるが、それは“共同の父母”として考えればよいと思う)から聞き、エンピツを原稿に走らせたのである。
その1行1行は、戦争に対する“激しい憎しみ”と、そして平和に対する“心からの叫び”が込められ、胸を打つものがあった。「小学校編」73編、「中学校編」21編、「高校編」20編の計114編。その中の一、二を紹介すると――。
「戦争とは何なのだろうか。人間が人間を殺しては喜び、相手がみじめになるほどつけねらってくる。いったい何の理由があって」(渡辺真理、宮の原中学1年)「二荒山神社前に立つと視界をさえぎるものは何もなく黒い廃墟だけが横たわっていた……焼け跡からは、白いけむりが幾条も……」(小宮紀子、宇都宮女子高校2年)
これらはほんの一例であるが、どの体験も胸に迫ってくる。“創作”とはいえ、すごい迫力である。
■草の根民主主義
同じように、菅野さんの指導の下で行った父母から聞いた「子どもたちの空襲体験記録」も恐らく、力作が多かったに違いない。当然、沖縄における教研の全国集会は、原爆体験と沖縄体験の継承がひとつの議題になったのだろうが、東北の片田舎の空襲を掘り起こすという、この地道な平和教育も注目されたのはいうまでもない。
菅野さんのリポートには、特別な惨禍を受けた人ではなく、ごく普通の人の戦争の話が綴られていた。目を見張り、耳をそば立てるような内容など全然ないリポートである。
「普通と思われる人、あるいはその周辺にいる人の話をよく聞くと、必ずといっていいほど、戦争とのかかわりを持っているものです。私は、その普通の人の話を綴っていくことが平和を守る道につながると思います」
片田舎における、わが町わが村の“私たちの戦争体験”を掘り起こし、等身大の戦争を伝えていく――。これが草の根民主主義というものなのかもしれない。
片野 勧
1943年、新潟県生まれ。フリージャーナリスト。主な著書に『マスコミ裁判―戦後編』『メディアは日本を救えるか―権力スキャンダルと報道の実態』『捏造報道 言論の犯罪』『戦後マスコミ裁判と名誉棄損』『日本の空襲』(第二巻、編著)。近刊は『明治お雇い外国人とその弟子たち』(新人物往来社)。
関連記事
-

-
『リーダーシップの日本近現代史』(46)記事再録/『江戸を戦火から守った西郷隆盛と勝海舟、高橋泥舟、山岡鉄舟の(三舟)の国難突破力①』★『『人、戒むべきは、驕傲(きょうごう)である。一驕心に入れば、百芸皆廃す』
2011/06/04 日本リーダーパワー史(157) &n …
-

-
速報(363)『日本のメルトダウン』低線量被曝の現状●市民と科学者による内部被曝者問題研究会の会見『福島のチョウの奇形』
速報(363)『日本のメルトダウン』 <3/11から1年ヵ8月―低 …
-

-
「Z世代のためのウクライナ戦争講座」★「ウクライナ戦争は120年前の日露戦争と全く同じというニュース]⑥」『開戦37日前の『米ニューヨーク・タイムズ』の報道』-『「賢明で慎重な恐怖」が「安全の母」であり,それこそが実は日本の指導者を支配している動機なのだ。彼らは自分の国が独立国として地図から抹殺されるのを見ようなどとは夢にも思っておらず,中国が外部から助力を得られるにもかかわらず,抹殺の道を進んでいるのとは異なっている』
『日本戦争外交史の研究』/『世界史の中の日露戦争カウントダウン』㉚ …
-

-
『F国際ビジネスマンのワールド・ニュース・ウオッチ(141)』『ロシア機墜落ー中東情報は、やはりイギリスが早い。BBCの報道が常に他を圧しています」
『F国際ビジネスマンのワールド・ニュース・ウオッチ(141)』 『ロシア機墜落ー …
-

-
世界、日本メルトダウン(1021)ー「トランプ大統領40日の暴走/暴言運転により『2017年、世界は大波乱となるのか」①『エアーフォースワンはダッチロールを繰り返す。2月28日の施政方針演説では「非難攻撃をおさえて、若干軌道修正」、依然、視界不良、行き先未定、墜落リスクも高い①
世界、日本メルトダウン(1021) トランプの暴走暴言運転によって『2017 …
-

-
『日米戦争の敗北を予言した反軍大佐/水野広徳の思想的大転換➀』-『第1次世界大戦でフランス・連合軍とドイツ軍が対峠,70万人以上の戦死者を出した西部戦線随一の激戦地ベルダンを訪れた』
日米戦争の敗北を予言した反軍大佐、ジャーナリスト・水野広徳 &nbs …
-

-
速報(223)『日本のメルトダウン』 ★『小出裕章氏の福島市での講演会「子どもの明日]『対策本部の議事録作成)の犯罪」
速報(223)『日本のメルトダウン』 ★『小出裕章氏の福 …
-

-
速報(414)『日本のメルトダウン』【第3の矢・成長戦略】安倍首相会見(動画)『日銀が下した【真珠湾攻撃】決断』
速報(414)『日本のメルトダウン』 ◎【 …
-

-
速報(295)『日本のメルトダウン』●『5月3日 小出裕章さんのNY講演会の3本』◎『荒井聡(民主党原発事故収束対策プロ座長の会見』
速報(295)『日本のメルトダウン』 ●『5月3日 小出 …
-
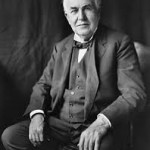
-
知的巨人たちの百歳学(108)ー『世界天才老人NO1・エジソン(84)<天才長寿脳>の作り方』ー発明発見・健康長寿・研究実験、仕事成功の11ヵ条」(下)『私たちは失敗から多くを学ぶ。特にその失敗が私たちの 全知全能力を傾けた努力の結果であるならば」』
再録・ 百歳学入門(96) 「史上最高の天才老人<エジソン(84)の秘 …
